|
今回から、老齢年金について説明していきますが、まずは、以下の図をみてください。
● 老齢年金の基本モデル
前提条件
夫 会社員 昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日
妻 専業主婦
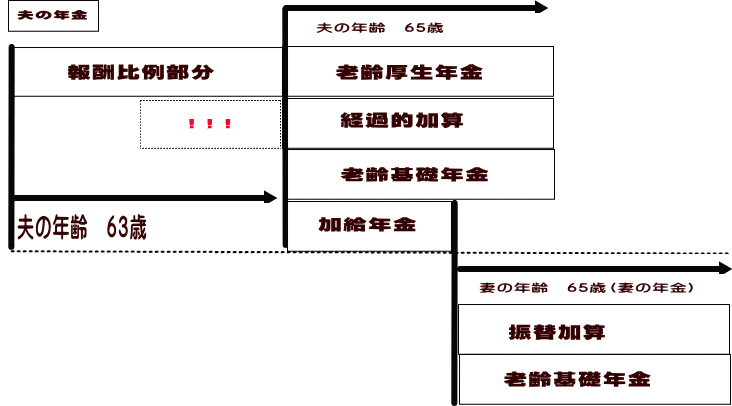
この図は、老齢年金の基本モデルと私が勝手によんでいるものです。老齢年金については、この先、学習を進めていけば、嫌でも分かると思いますが、ちょっと、複雑な制度になっています。初めて学習される方の場合は、
「さっぱり、わからない・・・」
との感想を持つのが、ごく普通だと思います。しかし、わからないままでは、FP試験に合格できませんから、年金制度の迷路に迷い込まないように、今、どの年金制度について学習しているのか、上記の図で確認しながらFP試験の学習を進めてみてください。簡単になるとは言いませんが、幾分、楽にはなると思いますよ。
ところで、この基本モデル、夫の生年月日が昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日生まれとなっていますね。
なぜ、この生年月日が選ばれているのか?
FP試験では、今年60歳となる男性の・・・・との質問がよくあるからです。
平成29年4月2日以降に60歳となる男性は、昭和32年生まれ。
この生年月日は上記基本モデルの生年月日に該当しますね。実は、65歳前に支給される特別支給の老齢厚生年金は、生年月日ごとに支給開始年齢が徐々に遅くなっていく仕組みになっているのです。
この前の生年月日の方の場合は、報酬比例部分の支給開始年齢は63歳となりますよ。支給開始年齢の違いについては、またあとで詳しく説明しますが、65歳前に支給される厚生年金の支給開始年齢は生年月日ごとに異なるという点は、おさえておくようにしましょう。
また、この生年月日に該当する方には、報酬比例部分とよばれる年金が支給されますが、以前は支給されていた
定額部分の支給はなし!!!
となっています。聞いたことがあると思いますが、年金財政は大ピンチ。昔のように大盤振る舞いで年金支給していたら、いずれ破綻してしまう・・・。そこで、生年月日に応じて段階的な支給開始年齢の引き下げが始まり、最初は定額部分の支給開始年齢の引き下げを行い、これが完了したので現在は報酬比例部分の支給開始年齢の引き下げをおこなっているというわけです。ちなみに・・・、今、支給されている65歳前にもらえる年金は、いずれ消滅します・・・。
ま、このお話はまた後日。今は老齢厚生年金のお話しは後回しにして、まずは、老齢基礎年金の内容について説明していきましょう。今お話しした支給開始年齢の引き下げは厚生年金から支給される老齢年金のお話。
ここで、お話しするのは老齢基礎年金のお話しです。前ページにあった年金制度の概略図では、1階部分に国民年金とありましたよね?ここから、支給される老後用の年金が老齢基礎年金です。国民年金と厚生年金を混同しないようにしてくださいね。では、国民年金から支給される老齢基礎年金の概要についてお話ししていきましょう。
国民年金制度は、原則として、

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者のすべてに加入義務
があり、この間に一定の受給資格期間を満たすだけの期間がなければ老齢基礎年金を受け取ることはできません。サラリーマン・OL等会社勤めをされている方の場合は、自分で手続きをする必要はありませんが、会社をやめて、個人事業主になる等であれば、自分で手続きをしておかないと将来年金がもらえなくなってしまうかもしれないのです。
では、ここで最初の図をみて、何歳から老齢基礎年金がもらえるのか、確認しておきましょう。
老齢基礎年金の文字がどこにあるのか探してくださいよ。
こうやって、何度か探しているうちに図が頭にはいりますから。
ありました?
65歳から(正確には、65歳の誕生日の前日)ですね。では、次に、65歳から老齢基礎年金を受け取るため要件となる受給資格期間についてみておきましょう。

受給資格期間=原則として25年以上必要
(※ 平成29年8月1日からは、受給資格期間は10年以上に短縮されました。)
受給資格期間=保険料納付期間+保険料免除期間+合算対象期間
・保険料免除期間とは?
生活保護をうけている、障害年金年金の受給権者等の理由により、保険料の納付の免除をうけた期間
・合算対象期間とは?
年金額には反映されないが、加入期間のカウントには加える期間のこと
・国民年金の保険料は?
平成29年度(平成29年4月以降)価額 = 16490円
※ 国民年金の保険料は、平成17年度以降、毎年度280円(平成16年度価額)ずつ引き上げられ平成29年
度以降の保険料は月額16900円(平成16年度価額)に固定される予定です。
まだ、学習をはじめたところですから、変な言葉がたくさん並んでいるあたりに覚えられない予感を感じているかもしれませんが、「受給資格期間は、原則として25年以上必要で、受給資格期間とは保険料を納付した期間だけを指すのではない」という、FP試験のポイントだけは最低限おさえておきましょう。
  


|
本ページには、FP技能士受験生が良い結果を得られるように、無料FP技能士ポイント講座をはじめとする様々な無料コンテンツが含まれています。受験生の方が、これらの無料コンテンツを利用してFP技能士試験の学習をしていただくことは、もちろんかまいませんが、無断転載、無断複製等については、かたくお断りいたします。
Copyright(c)2007年−2017年 1級ファイナンシャルプランニング技能士 星野直輝 All Rights
Reserved
|
| ![]()
